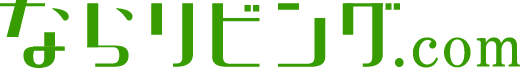犬の認知症~掛け替えのない存在だから~
認知症は人だけのものではありません。犬などの動物にも認知症は起こります。犬は家族同然に過ごしていることも多く、飼い犬が認知症になると家族も精神的・体力的に大きな影響を受けます。犬の認知症について、とみおペットクリニック院長の八板由巳子さん(51)に聞きました。

目次
犬の認知症とは
フレイルがアンバランスに
脳の老化は年齢を重ねれば、どの犬にでも起こることです。一方、自立生活を送れる状態から要介護状態への移行期のことを人と同じくフレイルと言いますが、認知症は脳のフレイルが先行して進行し、アンバランスになることで起こります。知的領域の機能低下が起こると、すべての行動に影響を与え身体機能の低下に。そのことからさらに脳機能の低下を起こします。
症状としては、時間や場所が分からなくなる「見当識障害」、物体や人の顔が分からなくなる「失認・失行」、物事を順序立ててできなくなる「遂行障害」、覚えられなくなる「記憶障害」という中核症状がまず起こります。
そして、そのことが原因で徘徊や不安感、攻撃、過食、不眠、興奮などの周辺症状が起こります。

犬の認知症は4段階に分けて考える
認知症は段階的に進みます。犬の認知症は、「要支援」→「要介護前期」→「要介護中期」→「要介護後期」と4段階に分けて考えます。それぞれの段階で認知機能、身体的機能、心理状態、行動の変化、家族の変化が起こります。

要支援の段階
できないことは無理させず
この時点では、まだ犬だけで留守番も可能です。認知機能としては、見当識障害が起こり時間や場所の感覚が分からなくなります。何かを探して歩き回ったり、いつもと違う時間にごはんを欲しがったり、散歩に行きたがる、トイレの失敗などが起こります。
身体機能では、足腰や姿勢に変化が起こります。内臓機能も低下し、気温や湿度など外部の環境に適応できなくなります。
心理的には、できることができなくなる不安感にストレスを感じます。できないことは無理にさせず避けた方が良いでしょう。
犬は自分でご飯を食べたり水を飲むこともできるので、取り立てて家族の生活に変化はありません。
要介護前期の段階
日常生活に支障が出始める
この時期には、犬は自分で移動はできるものの、日常生活に支障が出てきます。
認知機能としては、中核症状である見当識障害が強くなり、周辺症状でもイライラや不安、いらだちもあり落ち着かなくなります。反対に無関心になることもあります。
身体機能では運動機能の低下が起こり、ふらつきや転倒が起こります。心理的にも不安定になり、できないこと、分からないことが増えることから不安感や恐怖、焦燥などに見舞われます。自分の行動に自信がなくなることから、やめる判断ができなくなり、歩き続けたり、鳴き続けたり、徘徊行動も出てきます。昼夜が逆転して夜鳴きが始まるのもこのころ。過食や執着も出てきます。
家族も、犬の予期せぬ行動をしたり、狭い所に入り込むこともあるので常に気にしないといけなくなり、目が離せなくなります。
要介護中期の段階
緊張感が抜けない状況に
起き上がることはできるものの、介助が必要に。認知的にも自分の身体能力の低下を受け入れることができず、そのことが身体機能にも影響を与え、立つ、座るという姿勢を維持することが困難に。心理的にも不安感や恐怖、焦燥感が悪化し、逆の無関心も起こります。
脳のストレスも増えて、緊張感が抜けない状態に。寝てばかりいるため身体がこわばり、さらに緊張感が抜けなくなります。
思った動作や要求を達成できないことも増えてきます。動き始めに時間が掛かり、立つという動作をしている間に立つ目的を忘れてしまうこともあります。そうするとパニック状態になり、ひどく鳴くこともあります。
家族は、起き上がり等の基本動作に介助も必要になりますが、環境を整備することで目を離すことも可能になります。
要介護後期の段階
完全介護が必要で生活が犬中心に

日常生活全般に介護が必要になります。見当識障害や失認・失行、それに伴う周辺症状も進行し、心理的にも行動にも症状が出てきます。
寝返りや体重移動も難しくなり、時間の感覚や喉の渇きも分からなくなります。食事の時もお皿までの距離感や舌の使い方が分からず、微調整が難しくなります。動き回ることもできませんが、血流が悪くなり体温調整ができないため、配慮が必要になります。身体が固くなって不快感が増し、血行不良で代謝も低下。内臓機能の低下にもつながります。
激しい精神症状や激しい行動症状が起こります。一旦スイッチが入るとやめることが難しい状態に。また逆に心理的にも行動的にも無関心となることもあり、感情の起伏が見られなくなります。
この段階では、犬の飲食や排泄、温度管理など完全介護が必要になり、生活が犬中心に。家族の生活を正常に戻すことも必要になります。
認知症の犬のケア
年齢から脳の老化や体力を認識して

犬の認知症は正式には高齢性認知機能不全と言います。まず、犬の年齢を考えましょう。
20+(年齢-1)×4
が犬の年齢です。大型犬の場合は、
20+(年齢-2)×4
で計算します。
まず家族は犬の年齢を認識し、脳の老化や体力を認識することが大切です。
ケアの目的は、苦痛のない状態で穏やかに過ごせるようにすることです。
すべての段階で必要なことは次の4つです。
1・過度なストレスをなくし、適度な刺激を与えること
2・内臓の負担を減らすこと
3・生活習慣を整えること
4・水分不足に気を付けること
人間中心の生活になっているので、犬にとって無理がないか見直しも必要です。
ケアとしては、犬自身の身体感覚を鍛えさせることです。そのためには、全身を隅々まで触ること。肌から感じる感覚は脳へのトレーニングになり、固有感覚や神経への刺激になります。意識していなかったところを自分の体だと感じられるようになります。
次に、正しい姿勢で立たせること。立つ動作をすることで、筋肉や神経、血液循環、呼吸などさまざまな機能が働きます。自分で立てなくても、支えて立たせてあげましょう。
昼夜逆転と夜鳴きについて
昼間に生活音させマッサージを
認知症の相談で多いのが、昼夜逆転と夜鳴きです。
昼夜逆転については、夜に眠れるようにすることが目標です。日中屋内を明るくし、留守中もラジオやテレビなど生活音をさせておくこと。また寝ているポジショニングも大切です。ずっと同じ姿勢でいないよう、時々変えてあげましょう。
夜鳴きについては、夜に泣き続けないようにすることが目標です。そのためには生活習慣を見直すこと。こわばった、興奮しやすい体になっているので、昼間のうちに全身をくまなく触ってマッサージし、みぞおちの緊張を取ってあげましょう。昼間に起こしておくことが大切です。
まとめ
家族だけで抱え込まず早めに相談して予防を
「家族は自分たちだけで抱え込まず、専門家を頼ってちゃんとした治療を受けさせてほしい」と八板さん。とみおペットクリニックでは、DISHAAという認知機能評価シートも導入しています。何かおかしいと感じたら、早めに動物病院に相談することも大切です。
夜鳴きや徘徊、過食が始まってからでは、サプリメントなどでは治せません。犬は11~12歳の28%が、15~16歳の68%が1つ以上の認知機能低下が見られるとされています。犬の年齢を把握し、早めに受診すれば、要支援の間にサプリメントなどを与えるなど、予防することもできます。
認知症が進んでからも、頭を使わせることも大事です。お手やお座りなど、忘れてしまったことをもう一度覚えさせることも、脳に刺激を与えることになります。
また家族の環境の変化によっても、犬に掛かるストレス度合いは変わります。「犬に対する態度が変わっていなかったか、見直す機会を作ってほしい」と八板さんは話します。
☆ ☆ ☆
家族同然の存在として暮らしている犬や猫。年齢による老化は仕方ないことですが、できるだけのことはして、最期を迎えたいという方も多いのではないでしょうか。
記者の家でも、16歳を超えた柴犬に認知症の症状が出て、半年ほど経って天寿を全うしました。今回話を聞いて思い当たることは多々ありました。夜鳴きをしていたのは、不安や体の緊張からだったのでしょう。もっとマッサージなどしてあげたら良かったのかと、少し後悔も感じます。
これからは人の認知症と同様、動物の認知症も増えてくることでしょう。飼い主も動物の年齢や体力を把握して、予防と、早めに認知症の芽を見つけることが求められます。八板さんは「犬の認知症は予防が大切なので、8歳になったら検診を受けてほしい」とのこと。
かけがえのない存在だからこそ、最期まで大切に見守りたいですね。
取材協力/とみおペットクリニック
※このページの内容は2023年5月19日現在のものです。