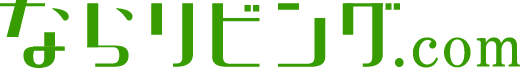漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~vol.39「不定愁訴」にお悩みの方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回は病気の診断はつかないものの、なんとなく体調がすぐれない状態「不定愁訴(ふていしゅうそ)」についてのお話です。

ストレスや生活習慣の乱れが大きく影響
体調不良やさまざまな不快な症状が続き、気のせいかな?と思ってやり過ごそうとしても日常生活にも影響が及ぶほどとなり、もしかしたら病気かも?と心配になって病院で検査を受けてみても明確な異常が見つからないという経験がある人もいると思います。
不定愁訴(ふていしゅうそ)の症状はさまざまで、身体的症状として頭痛、めまい、倦怠(けんたい)感、肩こり、動悸(どうき)、息苦しさ、胃腸の不調、耳鳴りなどのほか、不安感、イライラ、気分の落ち込み、不眠など精神的症状もみられ、人によって、また同じ人でも症状が変化することもあります。
胃腸の不調が出たら胃腸科へ、動悸がひどくなったら循環器科へ、息苦しさは呼吸器科へと対象の専門科を受診しては検査を受ける日々を過ごしてきたとの声も聞かれます。
不定愁訴とは、はっきりとした病気の診断がつかないものの、なんとなく体調がすぐれない状態を指します。原因はさまざまですが、ストレスや生活習慣の乱れが大きく影響し、自律神経のバランスが崩れることで症状が現れると考えられています。
病院で異常が見つからない不快な症状
更年期の女性ではホルモンバランスの変化も不調の一因となることがありますが、思春期や妊娠・産後にも起こることがあります。また、職場や家庭でのストレス、不安やプレッシャーが蓄積することで、頭痛やめまい、倦怠感などの症状として現れることも少なくありません。その他、季節の変わり目や気圧・湿度の変化によっても体調が悪化するケースもあります。
例えば「仕事が忙しくなると頭痛や肩こりがひどくなり、病院で検査を受けても異常がないと言われる」「朝から疲れが抜けず、やる気が出ない」「理由もなくイライラしたり、不安になったりする」「ストレスが続くと胃がムカムカし、食欲がなくなる」などの訴えがよく見られます。病院で異常がないと言われても、ご本人にとってはつらい状態が続いており、多くの場合「周囲に理解されにくい」「病院で異常が見つからずかえって不安になる」などの悩みを抱えておられます。
自律神経の安定には生活習慣の見直しから
自律神経の乱れと言われてもどう対処すればよいかと悩まれる方は、まずは生活習慣の見直しから始めてみましょう。自律神経は体内時計のような存在でもあり一定の決まったリズムで動いていると安定した状態が維持されます。
睡眠は就寝時間、起床時間を一定にして寝不足にならないよう睡眠時間を確保しましょう。
食事もある程度決まった時間にとるようにし、特に夜遅くに食べ過ぎたり極端なダイエットなどは控えたほうが好ましいでしょう。
適度な運動は、ストレスを発散して気分転換にもなり、自律神経の安定にも効果的です。深呼吸や温かいお風呂などを日常に取り入れることで、リラックスしやすくなり少しずつ症状が和らぐこともあります。
漢方薬やサプリメントも使用して心と体のバランスを
さらに、漢方薬やサプリメントを活用するのも一つの方法です。
漢方の場合は「未病」という考えがあり、不定愁訴のような「病気ではない不調」の改善に適しています。
不定愁訴は、自律神経の乱れやストレス、ホルモンバランスの変化などが関係すると言われていますが、漢方では「五臓(肝・心・脾・肺・腎)」のバランスが崩れると、さまざまな不調が現れるため、症状からどの臓腑に不調があるかを知ることができます。
●「肝(かん)」の乱れ:ストレスや情緒の不安定
肝は「気(エネルギー)」の巡りを調節し、精神の安定に関わります。肝の働きが乱れると、気が滞りやすくなり、イライラや落ち込み、不安感が強くなることがあります。さらに、頭痛や肩こり、目の疲れ、生理不順なども肝の不調と関係しています。
対策:リラックスできる時間を持ち、深呼吸やストレッチも効果的。ストレスを溜め込まない工夫をする。
●「心(しん)」の乱れ:動悸や不安、不眠
心は血の巡りを管理し、精神活動を司るとされています。心の働きが弱まると、動悸や息切れ、不眠、焦燥感、胸のザワザワ感などが現れることがあります。特に、ストレスが長引くと心のエネルギー(心気)が不足し、不安が強くなりやすくなります。
対策:十分な睡眠をとることが大切。心を落ち着ける習慣を持つよう調整する。
●「脾(ひ)」の乱れ:消化不良や倦怠感
脾は消化吸収を担い、エネルギー(気)を生み出す役割があります。脾の働きが低下すると、胃もたれや食欲不振、下痢や便秘、疲れやすさ、集中力の低下などの症状が出やすくなります。ストレスで胃の調子が悪くなるのも、脾の不調が関係しています。
対策:消化に優しい食事を心がけ、よく噛んで食べる。
●「肺(はい)」の乱れ:息苦しさや倦怠感
肺は呼吸を通じて気を巡らせるとともに、体のバリア機能(免疫力)にも関わります。肺が弱ると、息苦しさや浅い呼吸、疲れやすさ、風邪をひきやすいなどの症状が出ることがあります。また、気候の変化に影響を受けやすいのも肺の特徴です。
対策:呼吸を意識し、ゆっくり深く吸う習慣をつける。温かい飲み物を摂り、肺を潤すと効果的。
●「腎(じん)」の乱れ:疲労感や冷え、老化症状
腎は生命エネルギーの貯蔵庫のような役割を持ち、成長やホルモンバランス、老化とも関係があります。腎が弱ると、慢性的な疲れやだるさ、足腰の冷え、抜け毛や白髪、不眠、むくみなどの症状が現れやすくなります。更年期の不調も腎の衰えと深く関係しています。
対策:体を冷やさないようにし、温かい食べ物や飲み物を摂る。
不定愁訴は、病院の検査では異常が見つからないことが多いですが、漢方の視点から見ると、五臓のバランスの乱れが原因となっていることが多いです。生活習慣の見直しや漢方を取り入れることで、不調を改善できる可能性があります。
もし症状が長引いたり、日常生活に支障をきたすほどつらい場合は、内科や心療内科、婦人科などの医師に相談したり、自分の体質に合った漢方を専門家と相談しながら利用するなど、心と体のバランスを整えていきましょう。不定愁訴は軽視されがちですが、放置すると悪化することもあるため、早めのケアを心がけましょう。
※このページの内容は2025年3月21日現在のものです。